「友達とカラオケに行って歌っていたら、『おまえ今のオク下じゃん。ダッサ!』とバカにされました。でも自分には何がどうダサいのかわかりません。どうすればいいのでしょうか?」
こんな質問がよくネットに挙がっています。
自分は気持ちよく歌っていたのに「ダサい」と言われたら傷つきますし、初心者さんではなぜ誹謗されるのかもわからず、困惑しちゃいますよね。

このページではそんなお悩みを軽減するヒントを得るために、オク下が「ダサい」と言われる理由を詳しく説明していきます!

昭和の時代からカラオケの楽しみ方を追求してきた管理人キー太郎にお任せください!
※こちらもご参考にどうぞ!【オク下とは何か・オク下の確認方法・オク下の改善方法・オク下批判のかわし方】
「無自覚オク下」がダサい? そもそも「ダサい」ってどういう意味?
オク下の中でも「ダサい」と言われやすいのは「無自覚オク下」で、言われた本人はオク下で歌っている自覚がありません。
さらに「オク下」という言葉すら知らない場合も多いので、非常に当惑することが多いようです。
一方で「ダサい」という言葉ですが、本来この言葉は「恰好が悪い、野暮ったい、 垢抜けない」などの意味に使われてきました。

つまり「見た目が悪い」「流行りに乗れていない」「都会的でない」などという感じなのでしょう。

でも、それがなぜオクターブ下で歌うことについて言われるのでしょうか?
オク下が「恰好が悪い、野暮ったい、 垢抜けない」と批判されるのにはいくつかの理由があり、それは今後のオク下への批判をかわすヒントにもなりますので、ここで細かく見ていきましょう。
音高が低いと聴く側が「盛り上がらない」という批判
高音曲のイントロが流れれば、参加者は高音の歌唱でテンションが上がることを期待しますが、これを1オクターブも下で低く歌われると「盛り上がらない」「期待はずれだ」と感じてしまいます。
犬の「ウォォォォ~ン」とかん高くロングトーンで鳴く「遠吠え」は他の犬にも容易に興奮を呼び、連鎖的に広がっていくことがあります。

このように「高音を聴くと興奮する」というのはヒトがヒトになる以前からの「動物一般の習性」かもしれないので、正直こればかりは避けようがない批判なのかもしれません。
「ダサい」の中には、こんな原始的な反応もあることも覚えておいた方がいいでしょう。
「音感が未熟」「無自覚なのが未熟」という批判ってどうなの?
本来は批判することでもされることでもありません。
結論から言うと、批判する人がオク下で歌う人(以降「オク下さん」)をライバル視しているだけです。
初めは誰もが未熟者ですから、カラオケを始めたばかりの人の中には音感が未熟なままの人もいれば、それに気がつかない人がいるのも当然です。

できる人はできない人に教えてあげればいいのですが、その前にとくに男性は相手にマウント(詳しくは次の見出しで)をとりたいのです。
でも無自覚のオク下なんて、新品の服をはじめて着るとき、急いでいて襟の後ろに値札がついたままだったのに気がつかなかった程度のことですから、気がついた人はそっと教えてあげるくらいの大人対応がスマートじゃないかと思うんですが、ライバル視している人にはそれができません。
これに対して、歌うことをよくわかっている人は、「音程の正しさ」よりも「歌う楽しさ」が優先される場面も大切にすることができます。
初心者のオク下を批判し、あからさまに自分の優位をアピールする人は「ライバル目線」っていうことですから、初心者とほぼ同格、自分も初心者の範囲をまだ出ていないということを自覚した方がいいかな、と思います。
マウントとは?
「マウント(あるいはマウンティング)」とはもともと動物行動学の用語で、群れで暮らす動物の間での「相手に対する自分の優位を示す行動」や、具体的に言えば「相手に覆いかぶさる動作」そのものなどを指していました。
たとえばサルの群れで、強いサルが弱いサルに対して後ろから覆いかぶさる動作は「俺の方がお前より強いんだ」「俺の方が地位が上なのだ」ということを示すマウント行動です。
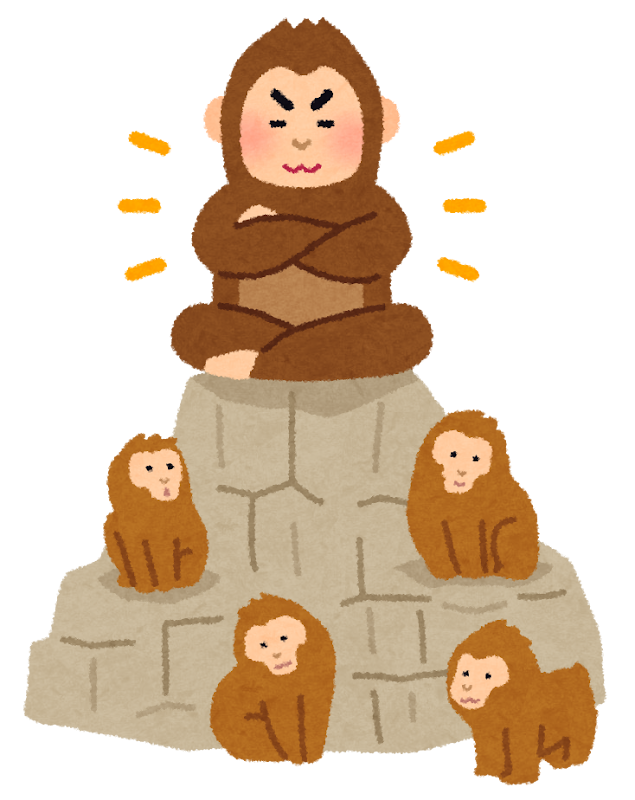
しかし最近では、人間関係を表す言葉として転用され「相手への優位を示す行動」全般を「マウント(をとる)」と呼ぶことが多くなっており、人間の動物的な行動に対して批判の意図を含んだ表現になっているようです。
ヒトは数ある動物の中でもとくに社会性が強く、高度で複雑な群れ(社会)を作ります。

「高度で複雑」というのは、分業が非常に進んで役割が多種多様であり、それらが緊密に連携し合って社会が成り立っているということです。
そのような社会では、各々の群れ(集団)がそれぞれの目的を共有し協調して動く必要性があるので、組織的な階層やさまざまな指揮系統が必要になります。

大勢のメンバーが協力できる群れの方が、目的の達成度は高くなりますからね。
そうすると、各々の集団や部署・場面ごとに「命令を出す者」と「命令に従う者」とをはっきりと分ける必要が出てきます。
このときオス(男性)は、群れの中の順位(上下関係)を明確にアピールすることで、指揮系統の紛糾を避け、秩序を保とうとします。

それは指揮系統の紛糾が大きくなれば、目的の達成度が低くなるだけでなく、群れ内での対立が喧嘩や内紛、そして群れが分裂してしまう可能性もあるからです。
このためにどうしても、あらかじめマウントをとって「優劣」や「順位」を周囲に示しておこうとする傾向が強いんですね。

これに対してメス(女性)は、目的達成によって得られた利益や権利を平等に分配することで、群れ内の秩序を保とうとする場合が多いように見えます。

ヒトの群れ(社会)は、このように「優劣・競争」と「平等・共有」が、動的にうまくバランスを保っているのではないでしょうか。
こういった男女の行動の傾向のちがいはカラオケにも現れることがありますから、よく観察してみましょう。
「流行に乗れていない」という批判ってどうなの?
ご存じのとおり、とくに2020年前後から男性の高音ボーカルのユニットが非常に注目されるようになってきました。
これらの高音曲を歌うということは、若い男性にとっては「流行の最先端を知っていること」しかも難易度が高く「『スゴイ!』と尊敬される行為」ということで、「その他大勢」から抜きん出るための方法として、憧れの対象になっているのだと思います。

そしてこのような方法を知らないことや、知っていてもその流行についてきていないことに対しても「ダサい」という評価がくだされているのではないでしょうか。
しかし歌というものは「流行」についてきてさえいればよいのでしょうか?
このような疑問に対して、江戸時代前期の俳人である松尾芭蕉は、よい俳句に必要なこととして「流行(りゅうこう)」と「不易(ふえき)」という2つの概念を挙げています。

この概念は俳句だけではなくすべての芸術活動に通じる、シンプルで深いアドバイスになっています。
「流行」とは現代で言う流行とほぼ変わりなく、「その季節や時代ならではの『よい』ととらえらていること」です。
これに対して「不易」とは「どのタイミング、どの地域でも変わりなく『よい』と人間が感じるもの」を意味しています。
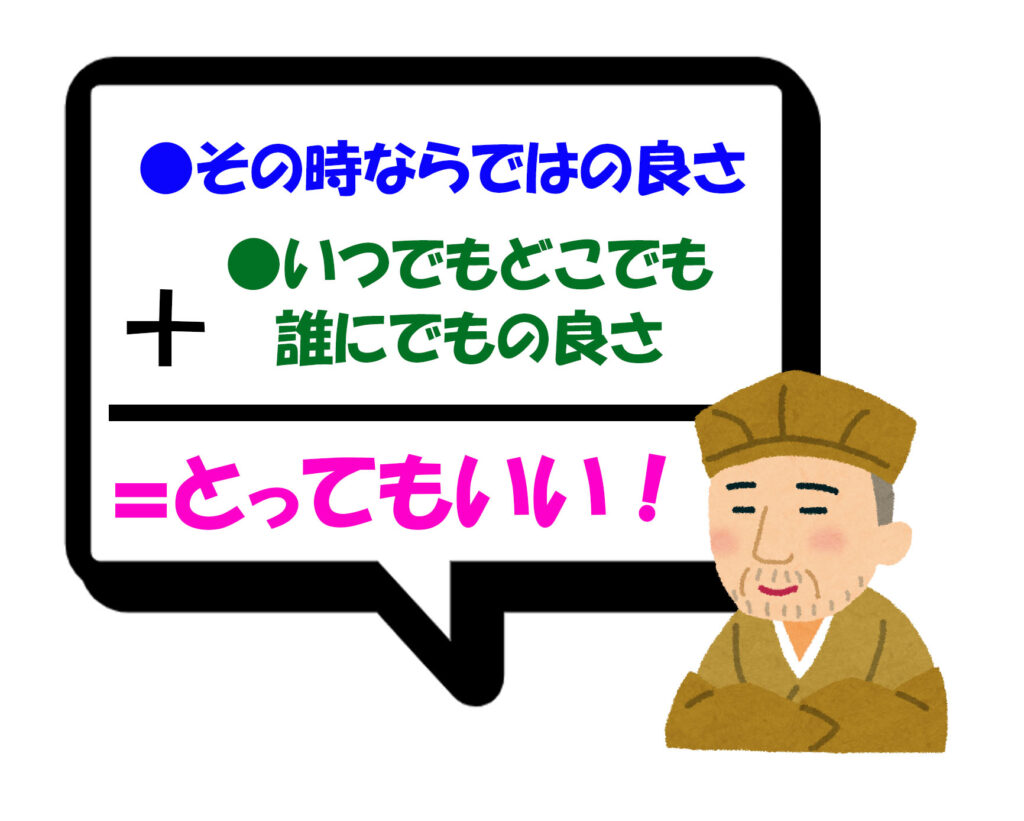
この2つの要素が揃っていることが、多くの人に「なるほど、大変良い!」と思わせるわけです。
先ほどは「高音曲を歌えることが、若い男性にとっては『その他大勢』から抜きん出るための方法として、憧れの対象になっている」と説明しました。
これは歌に求められている楽しみ方が「他と差別化できる」ということであり、競争心が強く興奮を求める若い世代ならではの特徴的なことですから「流行」的な楽しみ方と考えることができます。

では、歌に求められている楽しみ方の「不易」にはどんなものがあるのでしょうか?
時代や地域に関係なく、広く歌に求められている楽しみ方とは「強く心に残ることを、多くの人と共有できること」ではないかと私は考えています。
同じリズムに乗り、同じメロディに気持ちを動かされ、同じ歌詞の世界観に感動することで、他人と共感することが歌の「不易」なのではないでしょうか。

そして同じ歌を一緒に聴くだけでなく、一緒に歌った方が共感が強まるのは言うまでもありません。
このように考えたとき、多くの人が一緒に歌えない高さの歌というのは、「高音での興奮」や「競争での差別化」という「流行」の面は満たしていますが、一方では「一緒に歌って歌の世界に共感する」という「不易」の面を満たすことはあまりできていないということになります。
つまり、現在流行している「ハイトーンの歌」は、人と人とをつなげるのではなく、人と人とを差別化する歌というわけです。
これに対して、そのような歌をオク下で歌って参加する人や、オク下で歌う人を受け入れて一緒に楽しめる人は、逆に「流行」の歌を「不易」として楽しむことができるわけですから、むしろ「歌の『不易』を体現できている人」として、高く評価されてもいいのではないでしょうか?
ハイトーンの歌を原曲キーで独唱できる人は「自分ひとりが幸せになる人」ですが、ハイトーンの歌をオク下のキーで「一緒に歌おう♪」と言える人は「他人も幸せにできる人」の可能性がある、というわけです。
高音曲を歌えるというステータスの争奪戦
このように若い男性にとって高音曲を歌えることは、ひとつのステータス(地位や優位性の証明)になっているようです。
しかしこのとき「俺、この曲歌えるよ。楽勝!」などと言った人がオク下で歌った場合にはけっこう大きな非難を浴びるようです。
「俺、この曲歌えるよ。楽勝!」というのがすでに周囲の男性から見れば「優位性の主張」という解釈になり、気持ちは「競争モード」になってしまいます。

「ふ~ん、その実力を見せてもらおうじゃないか!」というわけですね!

ところが実際に歌ってみたところ、オク下歌唱では「高音曲が歌えた」ということにはなりません。
また高音での興奮を期待していた周囲は、わりと大きな「肩透かし」を食らった気持ちになります。
すると周囲は「競争を仕掛けたのはそっちなのに、適切な方法で優位性を示してないじゃん?そんなの認められない。君の方が下だ!」というクレームをつけたくなり、このような思いが「ダサい!」という一言に加算されるのではないでしょうか。
オク下で得点をとるのはルール違反!?
さらに「高音のステイタス」がカラオケ採点にからんできた場合には、歌ったあとに「オク下で得点をとるのはルール違反!」と言われ、一方的に「反則負け扱い」をされる恐れがあります。

いや、それ「後出しジャンケン」のレベルですが(笑)。

しかし「ルール違反!」と批判する人は、なにも「自分の不利益」だけを気にしているわけではなく「参加者全員の不利益」を、言い換えればその場の「平等」や「秩序」を重んじている場合も多いかと思います。
カラオケの場には「流行と不易」でお話したように「歌う楽しさを共有する方向」と「歌うことで優劣を競う方向」が混在しています。
そして「マウントとは?」でお話ししたとおり、男性は群れの中の順位(上下関係)をはっきりさせたいですから、カラオケでも優劣をつける「勝負事」にしたり「小競り合い」をやることがあります。
そのような方々にとって優劣の判断が厳密であることは、「小競り合い」を「大げんか」にエスカレートさせないための必須条件であり、その場の「平等」や「秩序」のための「知恵」なのです。

たしかに「原曲で指定されたとおりの音の高さ」で頑張って歌った人からすると、オク下歌唱は「原曲で指定された高さではない」わけですし、それも±1~2程度ではなく-12なわけですから、同列に比較されたら面白くないことはわかりますよね。
オク下歌唱への批判には、実はこういった「優劣のうえでの秩序を重んじる」という心理があることも理解しておきましょう。

でもやはり、「競争」や「差別化」とは別方向にある「共有」「共感」を忘れてしまったら、歌はその役目の半分を失うことになります。
くり返しになりますが、競争・差別化のうえでオク下は「反則」や「減点」であっても、共有・共感のうえでオク下は「重要な選択肢のひとつ」でもあることも、忘れたくないですね。
まとめ
こうして細かく見ていきますと、オク下歌唱への批判は①音高が低いと聴く側が「盛り上がらない」以外の項目は「マウント」とか「順位」が関係しており、男性の「マウントをとりたがる習性」が強く影響していると考えてよいかと思います。
・・・少なくとも私は、女性が女性のオク上歌唱に対して「ルール違反」とか言って批判したり(または批判されたり)、あるいは女性が男性のオク下を「ダサい」と指摘したという記事や質問は見たことがありません。
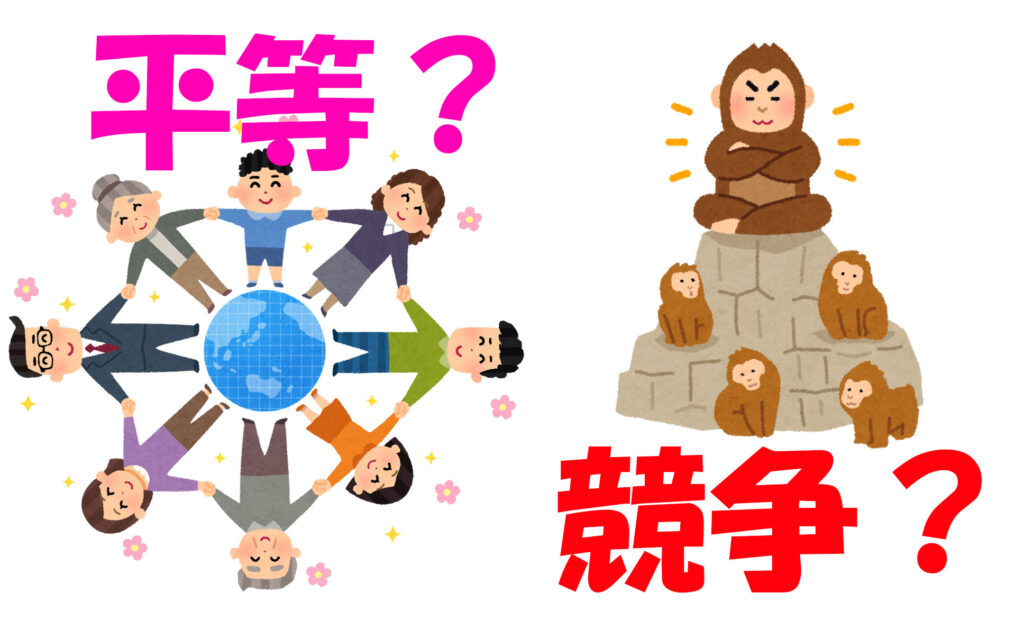
やはり「私たちはみんな平等を尊重してるよ」「共感が大切だよ」という女性の態度は、競争ばかりしたがる男性の態度とバランスをとり、その場を安定させる力があるのではないでしょうか。
また、ハイトーンの歌をオク下で歌うことを楽しめる人は、歌を「競争・差別化」の手段ではなく「共有・共感」の手段として扱える「楽しい人」になれる可能性があります。
このように考えますと、カラオケの場において「オク下批判」をかわしたり和らげたりする方法は、なんとなく見えてくると思います。
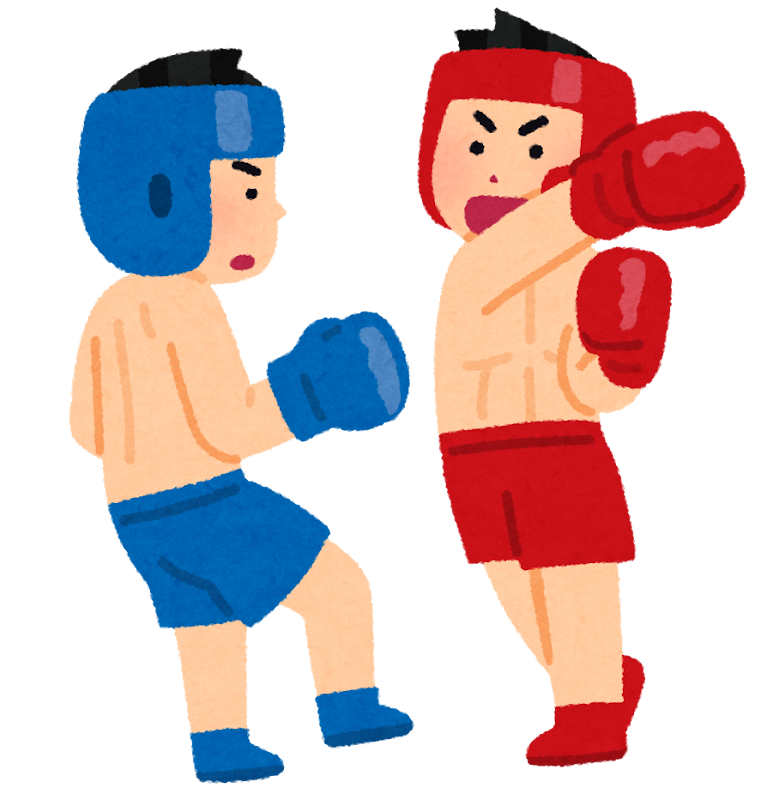
その対策は【オク下批判のかわし方】にまとめてみましたので、ぜひ読んでみてくださいね!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!




コメント